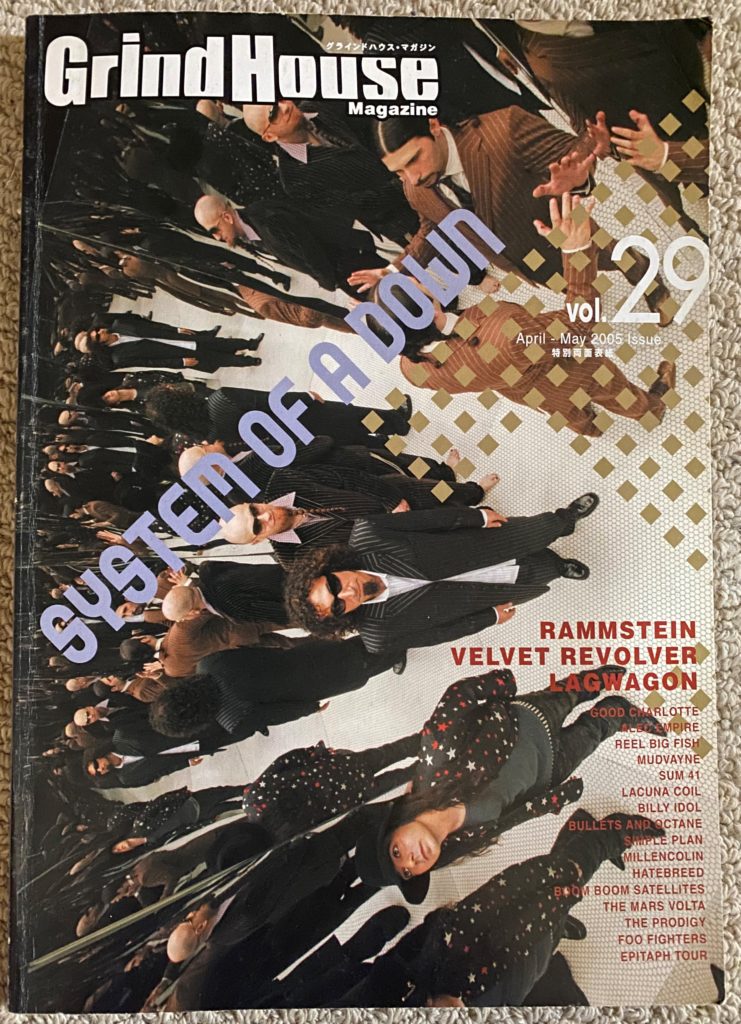【2021.06.02更新】
MuDvAyNe再結成を祝し、インタヴュー記事再公開第3弾だ。
text by Hiro Arishima
translation by Itsuko Ishimura
新作は『L.D. 50』と『THE END OF ALL THINGS TO COME』のクロスオーバーって感じかな
ニューメタル・ムーヴメントの動きを引っ張り、華麗に彩った数多のバンドの多くがその後急激に失速し、淘汰されたなかで今なお、このMUDVAYNEは異彩を放つ。“ブルータル”なる言葉が頭をよぎるほどヘヴィでアグレッシヴなサウンドのなかで美旋律を極め、並行してインテレクチュアルでもあるそのスタイルは、彼ら独自のものだ。メジャー移籍後第3弾となる『LOST AND FOUND』発売を期にギターのグレッグ・トリペットに電話インタヴューした。
ーー前作『THE END OF ALL THINGS TO COME』(邦題『ヘヴィロック断末魔』)以来2年半ぶりの新作を完成させた今の心境は?
「今はスゴくワクワクしてるし、最高の気分だよ。早く新作が発売され、それでまたいろんなところをツアーしたい。新作は最高の出来だから、きっとみんな気に入るはずさ」
ーー今、前作を振り返ってみて、あなたにとって音楽的にどんな作品だったと思います?
「満足してるよ。ひとつ心残りなのは、日本にいけなかったこと。今回は絶対にいくつもり。まだ確かじゃないけど、6、7月ぐらいにはまた日本でライヴがやれるはずさ。前回はもう4年も前のことになるんだよね」
ーーアーティストたるもの、どんなに自分で納得した作品ができたと思っても、心のどこかに「あそこをこうすればよかった」っていう想いがあるのも、また事実でしょう。新作制作中にそうした前作の想い、心残りを踏まえて取り組んだってことはありました?
「そうだね。今回はもっと曲構成に力を注いだ。個人的には曲を作る際にいろんなコード進行を試してみたり、チャド(・グレイ)のヴォーカルの活躍の場を以前より持たせるように心がけた。だからこれまでの作品よりもよりストラクチュアルな、凝った構成の作品に仕上がってる。ラウドなメロディをもっと上手く表現しようとしたら、こういう仕上がりになったんだ。いろんな面でオレたちは成長したよ。だから前よりヘヴィな部分と、メロディアスな部分の扱い方が上手くなってると思う。言葉でたとえるなら、新作はメジャーデビュー作『L.D. 50』(2000年)と前作のクロスオーバーって感じかな」
ーーあなたたちは長い活動キャリアを持ちます。よって基本的な曲作りのフォーマットっていうものがあると思うんですけど、それってどういうものですか?
「オレが曲を作るときは、まず最初にギターのリフが頭に浮かぶ。そのとき曲全体のイメージが沸くこともあるけど、基本的にはリフが浮かんだらそれをメンバーの前でプレイし、一緒にジャムる。その時点でだいたい曲のイメージは固まるけど、そうするとチャドが歌詞をつけはじめる。最後に、それらすべてをもう一度通してやってみて、それで曲が生まれるんだ」
ーー今回もそのやり方を踏襲したと?
「うん、基本的にはね。だけど、と同時に、並行して少し新しいことにもチャレンジしたよ。曲作りにはかなりの集中力が必要だから、今回は周りから邪魔されないような場所にいくことにしたんだ。で、カリフォルニアのド田舎の牧場にメンバー全員でいって、曲作りに励んだんだ」
ーーメジャーデビューしたときに盛り上がってた音楽シーンの動向と、今のそれとではだいぶ違います。曲作り、レコーディング時にそういうことを意識しました?
「イヤ、逆に無視することにした。だから片田舎の牧場なんかにいき、世間から遠ざかろうとしたんだ。そうでもしないと、結局はほかの大多数の音楽と似たようなものになっちゃうから。自分たちを今のミュージックシーンやラジオからシャットアウトしたんだ。そのおかげで、新作は自分たちのアイディアが100%反映された作品になったよ」
ーー今回プロデューサ-に、SUPERJOINT RITUALやEVANESCENCEとの仕事で有名なデイヴ・フォートマンを迎えました。その理由は?
「彼はその2バンドを手がけたことで、異なるふたつの世界を完璧に表現できるってことを証明した。SUPERJOINT RITUALでは粗削りな、ナマの音を上手く演出して見せたし、その逆にEVANESCENCEじゃ派手でケバケバしいくらいの音を表現した。オレたちはそのふたつの要素を使い分けることのできる彼の手際にホレ込んだのさ。オレたちの音楽には、その粗削りな世界と派手な世界とを巧みに往き来できる彼がピッタリだったんだ」
ーー『L.D. 50』がGGGarthで、前作がデイヴィッド・ボトリル、新作がデイヴ・フォートマンと、気づけば作品ごとにプロデューサーを代えてます。その理由と、そうすることの利点とは?
「とにかく新しい作品で新しい曲なんだから、サウンドも新しいのに限るってこと。毎回同じプロデューサーだと結局どの作品も同じサウンドになる。新しい空気を吹き込むには、やはりプロデューサーも作品ごとに代えるのがいいと思う。それが一番大きな理由だね」
ーー前作発売後にメイクを落とし、素顔でやるようになりましたね?
「別にメイクを止めたわけじゃないよ。ただ単に今のオレたちはメイクなしでやってるだけで、それが最終形ってわけでもない。これからも、またメイクしたくなったらメイクしてステージに出るつもりさ。素顔も、オレたちにとっちゃメイク顔と同じくらい強いインパクトを持つイメージだ。新作を作るにあたり、自分たちの成長を感じることができたし、今は怖いメイクをしたバンドっていうより成長したロックバンドっていう自分たちの一面に、よりフォーカスしてるだけ。結成時に比べ、ビジュアルより、音楽そのものに焦点が移ってきてる。だけど、次にオレたちのフォーカスがどこに向かうかわからない。もしかしたらまたメイク顔でステージに上がるかもしれないし、絶対またそういう日もくると思ってる」
ーー新作じゃついに本名を名乗るんですね。
「そう、そろそろいいかなと思って(笑)」
ーー新作、めちゃくちゃカッコいいですね。それまでのMUDVAYNEサウンドが次のレベルに到達し、ヘヴィでブルータルなところは徹底してヘヴィでブルータルに、メロディックでドラマティックなところは心底メロディックでドラマティックというように、あなたたちの持つさまざまな要素がさらに際立ってるように思いました。
「うん、新作はオレたちの成長を表した作品さ。過去2枚の作品でトータル6年もツアーをやった。メンバーとは家族や兄弟のような屈託のない付き合いだし、とにかくオレたちは大きく成長したと強く感じる。バンドの成長、ツアーの努力、それらが上手く反映されたのが新作なんだ」
ーー前々からあった“MUDVAYNEらしさ”がより明確かつ魅力的になり、完全に確立されたようですね。
「それはバンドの成長ともつながるけど、メンバーの結束がより強固なものになったからだよ。オレたちの音楽世界はオレたち4人でないと作り出すことはできないし、逆に4人がいれば、おのずとオレたちの音になる。だからひとりでもメンバーが欠けるようなことがあれば、オレたちの音楽は大きく変化してしまうと思うよ」
ーーあなたたちの音楽を聴くと、いつもインテレクチュアルな雰囲気を感じます。こういうのってなかなか出せるもんじゃないと思うんですけど、いったいどこから出てくるんでしょう。
「オレたちの音楽はネガティヴというより、むしろポジティヴなものだと思う。インテレクチュアルな雰囲気はオレたちの音楽が問いかけをベースにしてるから醸し出されるんだ。新曲“Happy?”だけど、そうしてみんなにいろんなことを問いかけ、それについて考えてもらうんだ。だからオレたち自身がインテレクチュアルかどうかってことは別にして、新作もまた、いろいろ考えることができる作品であることは確かだと思うよ」
記事を読んでもらえばわかる通り、グレッグはこのインタヴューでバンドの成長を強調した。『LOST AND FOUND』を聴いてもらいつつ、記事を読んでもらうと、グレッグの発言により説得力が増すと思う。
参考記事
※『L.D. 50』発売に伴う初来日時のインタヴュー※
https://grindhouse.site/archives-mudvayne/
※レギュラーコラム“落書き博物館”記事
https://grindhouse.site/archives-mudvayne_2/
※2ndアルバム『THE END OF ALL THINGS TO COME』発売時のインタヴュー part 1※
https://grindhouse.site/archives-mudvayne_3/
※2ndアルバム『THE END OF ALL THINGS TO COME』発売時のインタヴュー part 2※
https://grindhouse.site/archives-mudvayne_4-part2/
有限会社グラインドハウス Copyright (C) GrindHouse Ltd. All Rights Reserved.